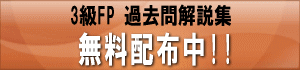問15 2018年5月実技(保険顧客)
問15 問題文
Aさんの相続等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 「契約者(=保険料負担者)および被保険者をAさん、死亡保険金受取人を推定相続人とする終身保険に加入されることをお勧めします。死亡保険金受取人が受け取る死亡保険金は『500万円×法定相続人の数』を限度として、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができます」
2) 「相続財産の大半が不動産であり、現物分割が難しい場合、自宅および賃貸アパートを取得する長男Cさんが、その代償として二男Dさんに金銭を支払うという分割の方法が考えられます」
3) 「自宅の敷地を妻Bさんではなく、同居する長男Cさんが相続した場合、当該敷地について小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けることはできませんので、注意してください」
問15 解答・解説
死亡保険金の非課税限度額・代償分割・小規模宅地の特例に関する問題です。
1)は、適切。生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税となります。
本問の場合、法定相続人は、妻と子2人の計3人ですので、死亡保険金のうち1,500万円までは非課税です。
2)は、適切。共同相続人のうち特定の者が被相続人の遺産を取得し、その他の相続人に代償として資産を交付する(遺産をもらう代わりに財産を分け与える)方法を、代償分割といいます。
遺産を相続した人は、その他の相続人に対して、財産を分け与えるという債務(特定の人に対して、一定の行為・給付をする法的義務)を負担することになるわけです。
3)は、不適切。小規模宅地の特例は、配偶者には、被相続人との同居や相続後の居住継続といった適用要件に制限がなく、必ず適用されますが、配偶者以外が取得する場合には、相続税の申告期限まで居住用宅地は居住・所有継続し、事業用・貸付用宅地は事業や貸付を継続することが必要です。
よって正解は、3
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
![]()
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士
![]() (資格対策ドットコム)
(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
![]()
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】
![]()
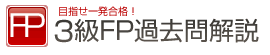
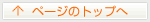
 ●無料アプリ版公開中。
●無料アプリ版公開中。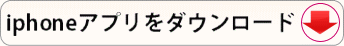
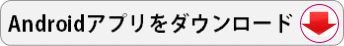
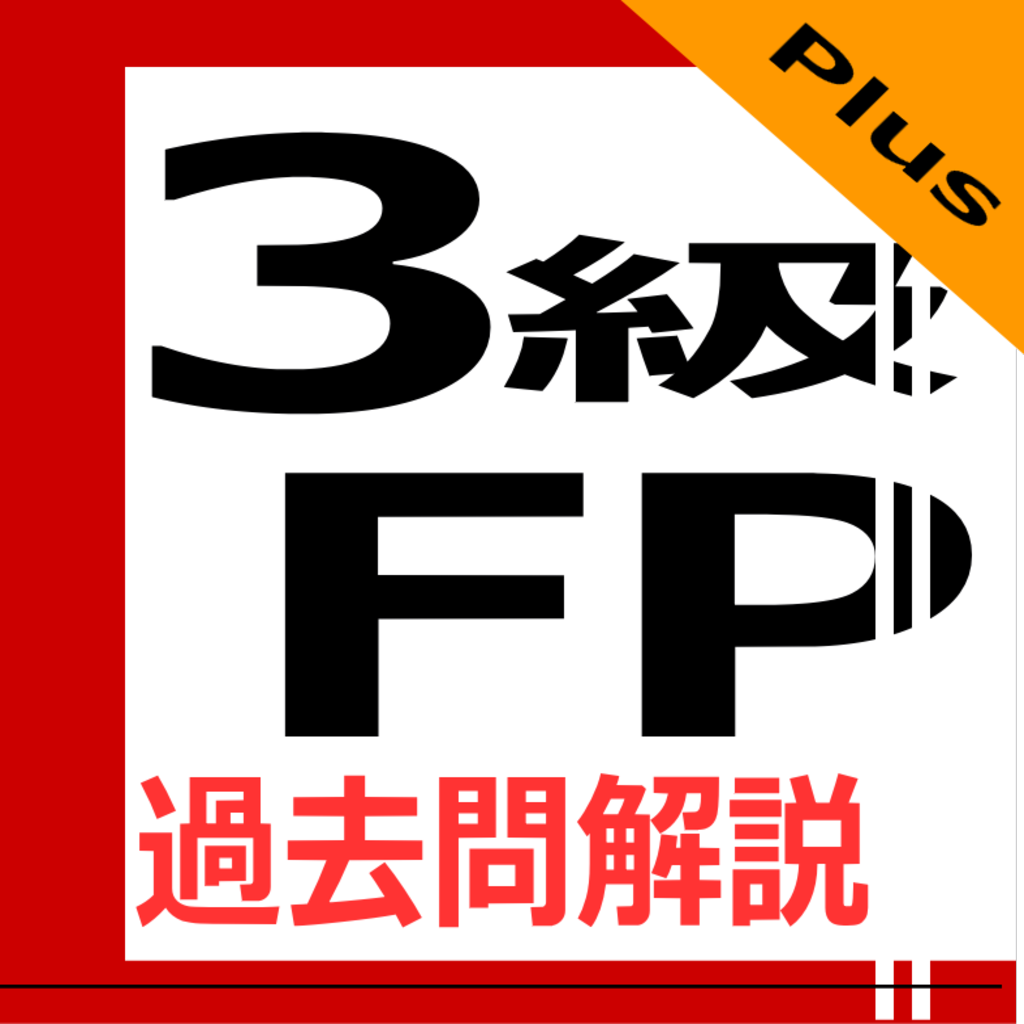 ●広告無しの有料版。
●広告無しの有料版。